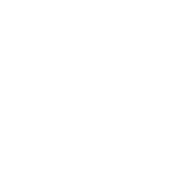空き家古民家の中でも改修して建物として再利用できる
ハイグレードな建物をここに掲載しています。
民家
住居として人が住むための建物
蔵
住居として人が住むための建物
神社・寺
公共の場としての性格が強く
コミュニティ空間として建てられた建物
民家

住居として人が住むための建物です。生業によって様々なタイプがあり、島根では大まかに農家と商家とがあります。
住むための空間の他にも、農作業や商売のための空間が設けられている場合があります。昔の大規模な農家や商家は現在でいう企業のようなもので、帳場や作業場、蔵、使用人の住まいなどが一体的につくられていました。
民家は、地域に根差して長い時間をかけて形づくられてきたものであり、その地域の風土や生業が色濃く現れる、いわば人々の営みの写し鏡であるといえます。
蔵

倉庫や保管庫として民家に付随して建てられた建築です。木で構造をつくり、外壁を土と漆喰で塗っています。
土や漆喰を塗る作業を「左官」といい、高い技術が求められます。島根県西部には左官技術が特に優れていたことから「石見左官」と呼ばれ、その漆喰装飾が全国に残っています(国会議事堂や最高裁判所等)。
島根に残る蔵の多くは、石見左官による仕上げがなされており、凝った造形となっています。
また、蔵は壁厚で断熱性が高いため、高い環境性能が求められる現代の住居やオフィスとしても転用が可能です。
神社・寺

近代化前の日本の神社仏閣は、宗教施設でありながら公共の場としての性格が強く、様々な寄合や催しが行われるコミュニティ空間として機能していました。
現在も自治会をはじめとする地域組織によって管理やメンテナンスが行われています。
しかし、地域の人口減少や高齢化が進んだことを背景に、管理が困難になり放置されるケースが多くなっているのが現状です。こうした神社や寺を、朽ちる前に何とか救出したいと考えています。